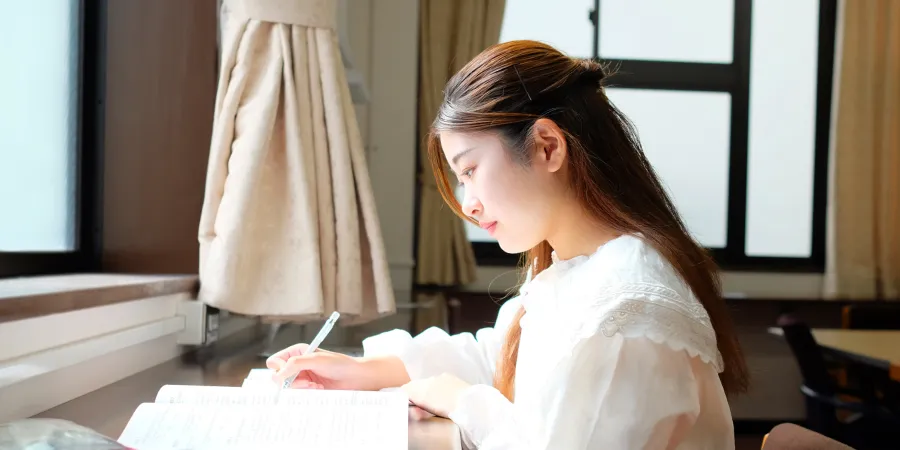平安女学院大学 学長
松尾光洋
平安女学院大学は「知性を広げ、望みを高くし、感受性を豊かにし、そして神を知らせる」という建学の精神のもと、キリスト教精神に基づく人格教育を通して、様々な社会課題に対応できる知恵と勇気を身につけた人材の育成に力を注いでいます。
国際観光学部では「京都文化」「ホスピタリティ」「語学」といった様々な切り口で観光学を学びます。子ども教育学部では保育士資格・幼稚園教諭免許・小学校教諭免許などの取得のための専門知識を学びます。これら専門的知識を実践する場として、両学部ともフィールドワークや実習、あるいはボランティア活動などの現場体験活動を重視しています。
現場活動のなかで課題を発見して、学んだ専門知識を関連づけて解決しようとする学問的探究を行い、それを社会に還元するために自ら進んで行動する勇気を持つことが望まれています。そのため本学は、少人数制のもと、学生一人ひとりと丁寧に向き合って、それぞれの良い面がより良い方向に延びて強みとなるように支援しています。どうぞ、安心して本学で学んで下さい。
松尾光洋 略歴
大阪市立大学大学院生活科学研究科前期博士課程修了。学術修士。
平安女学院大学子ども教育学部教授。
平安女学院大学子ども教育学部学部長を経て、現在に至る。
2025年3月21日
卒業生の皆さん、本日はご卒業おめでとうございます。ご家族の皆さま、また関係者の皆さまにおかれましても、心よりお祝い申し上げます。
皆さんは本学での学びを通じて、ディプロマ・ポリシーの卒業要件を満たされて、学位を取得されました。それがどんなに大変なことだったかは、この4年間を振り返って、ご自分自身がいちばん身にしみて感じていることでしょう。我々教職員としても、これほど嬉しく誇りに思うことはありません。4月からはそれぞれ社会人として自律してご自分の道をしっかりと歩んで下さい。
社会人になるにあたって、私から一言、励ましの言葉を述べたいと思います。
本学の卒業論文において、みなさんは論理的思考力を修得されました。論理的思考力とは、情報を整理し、筋道を立てて考え、合理的な結論を導き出す力です。しかし、現代社会では人工知能(AI)がこの論理的思考を非常に得意とし、人間を凌駕する場面も増えてきています。膨大なデータを解析し、最適な答えを瞬時に導き出すことに関しては、AIの能力は驚異的です。もはや、私たちがAIと単純に論理で競い合うのは難しい時代となりました。
しかし、だからこそ、私たち人間に求められるのは、AIには持ちえない人間的な「センス」です。センスとは、美しいものを美しいと感じ、適切な判断を直感的に下せる感性のことであり、他者への思いやりでもあります。たとえ作業を迅速に終えることができたとしても、センスが欠けた仕事は決して良い仕事とは言えません。なぜなら、仕事とは自分のためだけにするものではなく、誰かのために行うものだからです。仕事の成果物は、他者にとって「見やすく」「聴きやすく」「理解しやすい」ものでなければなりません。そのような配慮のある仕事こそが、真に価値のある仕事と言えるのです。
平安女学院大学は、キリスト教の精神を礎とし、人を思いやる心を育んできました。本学で学んだ皆さんには、この精神がしっかりと宿っています。そして、この精神は、他者を思いやるセンスとなり、社会で大いに役立つことでしょう。
特に、看護、介護、保育、教育といったケアワークの分野では、個々の状況や感情に応じた細やかなコミュニケーションが求められるため、AIによる完全な代替は難しいとされています。ケアワークだけでなく、接客等で個別にホスピタリティを必要とする職場もまたAIが苦手とする分野です。皆さんの多くは、こうした人と関わる職業に就かれるので、本学で培ったセンスを存分に発揮することによって、AIに負けない人間らしい温かみのある仕事をすることができるのです。
その際に大切にしてほしいのが、相手の感情に寄り添うことです。皆さんはこれまでの学びの中で、自分の意見を論理的に主張する力を身につけてきました。しかし、同時に大切なのは、他者にもそれぞれの考えがあり、その思いを受け止めることです。相手の立場に立って考え、相手の気持ちを理解する力が必要になります。この力のことを「エンパシー」と呼びます。
エンパシーとは、単なる同情や哀れみの感情である「シンパシー」とは異なり、相手の立場や経験を深く理解しようとする能力のことを指します。シンパシーは「かわいそうだ」と感じることですが、エンパシーは「この人がなぜそう感じるのか」「どのような背景があるのか」と考えることです。このエンパシーの力こそが、多様性のある社会を築くために不可欠な要素であり、皆さんが社会に貢献するための大きな原動力となると確信しています。
本学は今年、創立150周年を迎えました。その歴史は、1875年(明治8年)、アメリカの宣教師エディが大阪川口の地で英語を教えたことに始まります。以来、私たちはキリスト教の精神を基盤とし、教育を通じて暗きを照らす多くの女性を社会に送り出してきました。
皆さんは150年前のエディの学校の教え子たちの末裔として、その精神を受け継ぎ、これからの社会で活躍していく存在です。どうか、これからも学び続け、感受性を磨き、人と人とをつなぐエンパシーのある人間として歩んでください。そして、どのような道に進もうとも、本学で培った「センス」と「エンパシー」を大切にしながら、皆さんらしく、よりよく生きていかれることを願っています。神はあなたとともにおられます。
改めて、ご卒業おめでとうございます。皆さんの前途と世界が平安であることを、心よりお祈りいたします。
2025年4月1日
本日、平安女学院大学に入学された皆さん、ご入学まことにおめでとうございます。また、皆さんを支えてこられましたご家族や関係者の方々に、教職員を代表して、心よりお祝い申し上げます。
平安女学院は、米国聖公会から派遣された創立者エレン・ガードルード・エディによって、1875年(明治8年)に大阪の川口居留地で「エディの学校」としてその歴史の第一歩を踏み出しました。そして、1895年にこの京都の地に移転しました。以来、キリスト教精神に基づく人格教育を通して、さまざまな社会課題に対応できる知恵と勇気を身につけた女性の育成に力を注いできました。
大学は2000年に設置され、「知性を広げ、望みを高くし、感受性を豊かにし、そして神を知らせる」という建学の精神を掲げ、キリスト教の精神に基づく教育を通して、自由で自立した人格を形成するとともに、地域社会ならびに国際社会に積極的に貢献する人材の養成を目的としています。
本日入学された皆さんは、それぞれに、いろいろな夢や将来のイメージを抱いていることと思います。その夢が大学の目的である社会貢献と結びつくことで、皆さんの夢はより確かなものとなり、実現へと近づくと信じています。
社会貢献とは、人の役に立つということです。大学生活を通して、「自分にしかできない社会貢献とは何か」を見つけてください。
今は、夢と社会貢献が結びつかないと感じるかもしれませんが、この平安女学院大学を卒業する頃には、不思議なことに社会貢献できる力が身についていることでしょう。その理由について、ご説明いたします。
まず、大学は高校までの学びとは異なり、自律的に学ぶことを基本としています。自分の興味のある科目、好きな科目を好きなだけ履修できます。そこが大学の魅力です。
勉強が苦手だと感じる人もいるかもしれませんが、趣味など自分の好きなことに関しては、夢中になって色々と調べることは苦にならないはずです。例えば、好きな芸能人やアニメについて一生懸命に調べること、これは勉強しているのと同じです。大学では、そのような「好き」を学問として掘り下げ、常に疑問を持ち、追究し、より深く理解することを「学修」といいます。
まだ「好きなこと」が分からない人は、平安女学院大学で新たな「好き」を見つけましょう。平安女学院大学には、両学部に共通する教養科目に始まり、それぞれの学部でしか学べない専門性の高い科目まで、たくさんの科目を用意しています。ぜひ、これまでの勉強の概念を脱ぎ捨てて、「好き」になれそうな科目を見つけてください。これからは受け身の勉強ではなく、大学生活を通して「自分が本当に好きなこと」を見つけてください。
次に、好きなことを強みにしていきます。好きなことなら、自然と夢中になり、より深く学ぶことができます。それがやがて得意分野となり、あなたの強みへと成長していきます。その強みはあなたの個性となります。自分の強みを活かし、自分自身を好きになることができれば、将来のビジョンもおのずと見えてくるでしょう。
自分の強みを知っている人は、周りの人にもそれぞれに強みがあることが分かります。自分の強みを好きになれる人は、他者の強みも尊重できるようになります。これは、多様性を認め合うということにつながります。自分の強みを大切にする気持ちがあれば、他者の強みを尊重する気持ちも揺らぐことはありません。これは、「自分を愛し、隣人を愛する」というキリスト教精神に通じるものです。結果として、自然と社会貢献できる人材へと成長し、どのような分野や職種であれ、夢を実現する力を身につけることができるのです。
大学は、夢を叶えるための一過程と考えてください。本学では、夢は「見るもの」ではなく「実現するもの」です。そのために、毎日少しずつ知性を広げ、豊かな感受性を身につけて、明日の自分が今日よりも少し成長していることを少しずつ積み重ねていきましょう。
平安女学院大学の教職員は、あなた方、一人ひとりと向き合い、それぞれの良い面がより良い方向に伸びて、強みとなるように支援することをお約束します。そして、あなた方が、自分で自分の成長を促すことができるようにサポートします。
どうぞ、4年後には今日とは違った自分になっていることを想像して、これからの大学生活を楽しんでください。